アカデミー受講生の声
VOIX
1990年から開催している日仏音楽交流事業「京都フランス音楽アカデミー」には、これまで多数の受講生が参加し、いまでは多くの元受講生が国内外で活躍しています。
ここでは、アカデミーに参加した方々へのインタビュー記事をお届けします。
それぞれの音楽人生の中でアカデミーを通して得たものとは?
参加にご興味をお持ちの方は、是非ご一読ください!
(取材・写真・文/治部美和)
●受講生インタビュー
Vol.7 川崎梢さん(2025年 ピエール・レネール教授 ヴィオラクラス、ディアナ・リゲティ教授 特別演習 「Concerts fleuris - コンセール・フルリ」受講生)
 高校2年のときにヴァイオリンからヴィオラに転向した川崎さん。あたたかく豊かな音色に惹かれ、現在はヴィオラ専攻として日々研鑽を積んでいます。これまでなかなか機会のなかった弦楽三重奏やフルート四重奏に挑むため、3回目の参加となる今回は、ヴィオラに加えて、室内楽のプロジェクトにも参加。プロフェッショナルな演奏家と共に音楽をつくり上げる中で、「合わせる」だけでなく「共演する」ことの意識を深めたという川崎さんに、室内楽プロジェクトを中心に、お話をうかがいました。
高校2年のときにヴァイオリンからヴィオラに転向した川崎さん。あたたかく豊かな音色に惹かれ、現在はヴィオラ専攻として日々研鑽を積んでいます。これまでなかなか機会のなかった弦楽三重奏やフルート四重奏に挑むため、3回目の参加となる今回は、ヴィオラに加えて、室内楽のプロジェクトにも参加。プロフェッショナルな演奏家と共に音楽をつくり上げる中で、「合わせる」だけでなく「共演する」ことの意識を深めたという川崎さんに、室内楽プロジェクトを中心に、お話をうかがいました。
―今回の室内楽プロジェクトに参加しようと思ったきっかけは何でしたか?
弦楽三重奏やフルート四重奏を勉強できる機会が身近になかったので、少しでも経験が積めればと思い、参加しました。プロの教授と演奏できる貴重な経験ができることも魅力でした。プログラムが2曲とも古典派の作品だったので、アンサンブルの基礎を学べると思ったのも、理由の一つです。
―弦楽三重奏やフルート四重奏という、あまり日常的ではない編成に惹かれたのですね。さて、音楽を始められたのはお姉さんがヴァイオリンをされていたからだと伺いましたが、ヴィオラに転向するまでにはどんな経緯があったのでしょうか?
4歳からピアノを、5歳で姉と同じヴァイオリンを始めました。コロナが蔓延した高校生の時に、何とも言えない“閉塞感”というか、ヴァイオリンへの行き詰まりを感じて、師事している先生に打ち明けたところ、ヴィオラを勧めていただいたんです。練習するうちに、ヴィオラ特有のあたたかい音色が自分に合っているように感じて。前に出てメロディを奏でるのではない、内省的な部分が自分の性格に合っていたのかもしれません。大学はヴィオラ専攻で受験しました。
―今年でアカデミー参加は3回目とのことですが、ここでのプロジェクトは大学の授業や演奏会とはまた違った雰囲気だったのではないでしょうか。
はい。限られた2回のリハーサルと1回のゲネプロという非常に短い準備期間の中で、従来のような「教え・教えられる」関係性ではなく、先生自身の経験や音楽への考えをグループ全体に共有してくださり、メンバー全員で「共に創り上げていく」プロセスに大きな違いを感じました。また、プロの先生と舞台を共にできることは、とても貴重で光栄な経験でした。
―限られた時間だからこそ、密度の濃い関わり方になったのかもしれませんね。特に印象的だったアドバイスややりとりがあれば、ぜひ教えてください。
曲の背景について丁寧に語ってくださったことが、特に印象に残っています。たとえば、シューベルトの弦楽三重奏曲は、彼が10代の頃に作曲し、大きなホールではなく親しい人々が集まるサロンのような空間で演奏されることを想定していた、というお話がありました。モーツァルトについては、「歯切れよく、軽やかで愛らしい表現を」と繰り返し助言いただき、その音の立ち上がりや質感に対するこだわりがとても印象的でした。また、自分が伴奏にまわる場面と、主旋律に近い役割を担う場面とでの音量や音色の使い分けについての指導も、深く心に残っています。
―他の学生メンバーと一緒に演奏するうえで、川崎さんが大切にしていたことはありますか?
とにかくお互いがどのように演奏するのかをよく聴いて合わせていくことを大切にしていました。
―本番のステージも、そうした信頼の積み重ねが表れていたのではないでしょうか。当日はほぼ満席の状態でしたね。ステージからご覧になられたコンサートの雰囲気はいかがでしたか?印象に残った場面などがあればぜひ。
とてもあたたかい空気の中で、先生も一緒だからと安心して弾くことができました。自分のことだけに集中しすぎないで、周りを見ることもでき、心に余裕さえあったかもしれません。今まで本番を楽しかったと思うことは少なかったのですが、このコンサートはとても達成感があり、人とアンサンブルすることがこれほど楽しいのか、と思えるほどでした。
―まさに“共演”という感覚を得た貴重な機会だったのですね。プロの演奏家との共演のなかで、特に学びになったことはどんなことでしたか?
それまでは、室内楽において最も大切なのは「周囲にしっかり合わせること」だと考えていました。でも、実際には、ただ音を揃えるのではなくて、「共に音楽を創り上げていくこと」が何よりも重要なのじゃないかと気づかされました。作品の背景や作曲家についての理解を深めることで、音色やニュアンスにも説得力が生まれるということ、ヴィオラという楽器がアンサンブルの中でどのような役割を担い、場面ごとにバランスを見つけていくのかーそうした室内楽への向き合い方そのものも学ばせていただいたと感じています。
―そうした気づきを得て、ご自身の中で大きく変化したと感じる部分はありましたか?
今までは周りの楽器の邪魔にならないように気をつけて演奏していた気がします。でも、今回のプロジェクトで、一緒に音楽を作り上げることの大切さと楽しさを感じることができたことが一番の変化だと思います。周りについていくばかりではなく、「共演するんだ」という意識を持つことができたように感じます。
―その気づきは、今後さまざまなアンサンブルの場面でも活きてきそうですね。では最後に、これから同じような機会に挑戦しようとしている後輩たちへ、メッセージをお願いします。
先生と共演できることはとても貴重な経験です。教えていただく通りに弾くだけではなく、一緒に演奏する中でたくさん学ぶことがあるので、そういった機会にめぐり合ったときは迷わず挑戦してみてほしいです。
―ソロに限らず、室内楽やオーケストラといった“共に奏でる”音楽の中で、川崎さんがこれからどのような表現を育てていかれるのか、とても楽しみになりました。今年は大学最終学年という大切な一年、実りある時間となりますように。貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。


|
Vol.6 下村玄登さん(2025年 フローラン・エオー教授 クラリネットクラス受講生)
 高校からクラリネットを本格的に学び、演奏と音楽研究の両面での探究を志している下村玄登さん。自由な表現を促すフランス流の指導や、多彩な仲間との交流を通して、「演奏の引き出しが一気に増えた2週間」と振り返ります。大学院進学を機に、「演奏すること」「考えること」の両面から、音楽への理解を深め続けたい――そんな下村さんに、お話をうかがいました。
高校からクラリネットを本格的に学び、演奏と音楽研究の両面での探究を志している下村玄登さん。自由な表現を促すフランス流の指導や、多彩な仲間との交流を通して、「演奏の引き出しが一気に増えた2週間」と振り返ります。大学院進学を機に、「演奏すること」「考えること」の両面から、音楽への理解を深め続けたい――そんな下村さんに、お話をうかがいました。
―クラリネットを始めたのは高校から、ということですが、音楽はいつから始められましたか?
6歳のときにピアノを習い、小学4年生でフルートにも少し触れました。その後、中学校の吹奏楽部でバスクラリネットを始めました。
―小さな頃から様々な楽器に触れてこられた中で、特に中学時代にバスクラリネットを選ばれた理由はなんだったのでしょうか?
主旋律ではなくて、低音を支える役割に魅力を感じたのだと思います。音楽全体を下から支えるようなポジションに惹かれて、中学3年間はバスクラ一筋でした。
―絶えず音楽を続けながら、あえて音楽高校ではなく普通科の高校を選ばれたと伺いましたが?
そうなんです。私立の普通科に進学しました。ただやはり音楽は続けたかったので、吹奏楽部に入部したのですが、小規模で経験者が少なかったからか、「バスクラができるならクラリネットもできるよね!」と言われ(笑)、そこからクラリネットに転向しました。「いつクラリネットを始めたの?」と聞かれたら「高校から」と答えていますし、実際、本格的に始めたのは高校からです。
―高校からクラリネットを始められて、そこから音大に合格されるまでの努力に、並々ならぬ努力と集中力を感じます。きっと、それまで積み重ねてきた音楽経験が大きな支えになったのではないでしょうか。この春からは大学院に進まれます。直前のこの時期に、アカデミーに参加を決めたきっかけを教えていただけますか?
大学の同門の先輩や同期に受講経験者が多かったことがきっかけです。門下全体で参加するような雰囲気があって、自然と「自分も受けてみよう」と思いました。大阪にいながら、京都で海外の先生のレッスンを受けられるという距離感も大きなポイントでした。実はエオー先生は僕の通っている音大の教授の一人です。ただ、4年間のうち、レッスンを受けたのは3回生のときの1度だけ。授業で忙しかったので、外部のレッスンを受ける機会もなかなかなく、クラリネット単体の講習に参加するのは、今回が初めてでした。
―実際にご自身が参加されて、いかがでしたか?
とても濃密な2週間でした。まず、生徒の幅が広い。関東の音大生とここまで密に交流するのは初めてで、非常に新鮮でした。同じ音大生でも、普段接点のない学校の学生の音を聴けたのは大きな収穫です。
―レッスンの内容で、何か印象深かったことはありますか?
音楽の「揺らがせ方」や「節回し」の捉え方が違うことです。言語が違うから、考え方も当然違ってくるのかもしれませんが、日本式の教育にはないような指導もあり、それがすごく刺激になりました。「こんなに大胆にやっていいの!?」と思うような提案もありましたが、それが自分の“引き出し”を増やしてくれます。演奏者にとって表現の幅が広がるのはとても大事なことです。
―例えばどんな点で下村さんの“引き出し”が広がったのでしょうか?
技術的な指導はもちろんですが、表現の自由度が高い曲-特に19世紀以前のロマン派あたりの作品は、演奏者に委ねられる部分が多いです。そうした曲での“解釈の幅”を教えてもらえたことが大きかった。
また、今回プーランクのクラリネットソナタも持ち込みましたが、楽譜に細かい指示が多くて、それをどう解釈して表現するかが自分の課題でした。プーランクのようなフランス人の作品は、先生の“主戦場”です(笑)。作品の背景に関してはもちろん、たとえばこのソナタは遺作で、初演されたときにはプーランク本人はもう亡くなっていたけれど、その初演の伴奏者とエオー先生が知り合い――たしか「師弟関係だった」とおっしゃっていたかな?―つながりがあったそうなんです。すごいことですよね! プーランク本人に近づいたような気持ちになれて、音符の意味合いが変わってくるんです。これまでだったら、楽譜を読んで理屈で「こういうものかな」って考えるだけだったのが、そこからさらにもう一歩踏み込んで、理論を超えられる。そういう指導を受けられるのは、本当に大きいことでした。
―エオー先生のレッスンがどれほど良い刺激を与えてくれたのかが伝わってきました。そのうえで、これから下村さんは大学院でどのように音楽と関わっていこうとお考えですか?
実は、音楽の研究に興味があります。
―音楽学ということですか?
はい。大学院では演奏だけでなく、音楽の研究にも取り組みたいと考えています。もちろんクラリネットに関係する内容になりますが、たとえばクラリネット作品への音楽史的アプローチとか。実は音大に入る時点で、音楽学の道に進むか、演奏に進むかで迷ったくらいなんです。とはいえ、演奏の裏付けは必要だと思っているので、そういう意味でも、現地の空気感が感じられたり、受講生それぞれの作品へのアプローチが直に見聞きできたりするこのアカデミーのような場は“引き出し”を増やすためにも、とても重要です。
―レッスンを終えて改めて感じることはなんでしょうか?
先生からだけでなく、生徒間の刺激がすごく大きかったことでしょうか。今回来て驚いたのは、関東からの受講生がとても多かったこと。フランス留学から帰国して受講しているという方もいらっしゃいました。学生だけでなくて、音楽を仕事にされているプロの方もおられて、生徒の幅がとても広かった。彼らから受ける刺激は大きかった。生徒同士の影響は、先生から受けるものと同じくらい大きいんじゃないかなと思います。
―では最後に。このアカデミーでの時間を、下村さんの一つの物語にするとしたら、どんなタイトルになるでしょうか?
めちゃくちゃ難しい(笑)。――――「刺激」、でしょうか。
―大学院という新しいステージで、アカデミーで感じた「刺激」が、演奏の喜びはもちろん、音楽を学び、考える楽しさにも広がっていくことを願っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Vol.5 若林めぐみさん(2025年 ピエール・レネール教授 ヴィオラクラス受講生、ディアナ・リゲティ教授 特別演習 「Concerts fleuris - コンセール・フルリ」受講生/パリ・エコール・ノルマル音楽院スカラシップ受賞者)
 幼少期からバイオリンとともに歩み、音楽の道を志す中でヴィオラへと転向した若林さん。愛知県立芸術大学音楽学部および大学院を修了し、現在はフリーランスとして、東海地方を中心にオーケストラの客演奏者や室内楽奏者として活動中です。初めてのフランス流レッスンに触れ、表現の幅を広げた貴重な体験を、「自分の音楽を深く見つめ直した期間」と振り返ります。そんな若林さんの歩みと想いをお聞きしました。
幼少期からバイオリンとともに歩み、音楽の道を志す中でヴィオラへと転向した若林さん。愛知県立芸術大学音楽学部および大学院を修了し、現在はフリーランスとして、東海地方を中心にオーケストラの客演奏者や室内楽奏者として活動中です。初めてのフランス流レッスンに触れ、表現の幅を広げた貴重な体験を、「自分の音楽を深く見つめ直した期間」と振り返ります。そんな若林さんの歩みと想いをお聞きしました。
―まず、音楽を始められたきっかけから教えてください。
4歳ぐらいから、母が使っていたバイオリンで遊んでいました。ピアノを習っていたわけでもなく、楽器の“はじめまして”がバイオリンでした。
―そこからずっとバイオリン一本だったのですか?
はい、大学受験まではずっとバイオリン。でも、音大の入試でヴィオラと併願して受けたら、ヴィオラで合格して(笑)。それが転機でした。
―大学進学を機に生まれ育った長野から愛知へ。生活も楽器も、新天地からのスタートだったのですね。
ヴィオラが自分の性格や身体に合っていたみたいです。音域が低めなのも、自分にはしっくりきました。クラスには穏やかな方が多くて、先生や門下生の雰囲気もとても柔らかい。私にはとても心地よかった。
―6年間じっくり学ばれ、オーケストラをはじめ、さまざまな形で演奏活動を続けておられる中で、アカデミーに参加しようと思われたきっかけは?
フランスに留学している友人がいて、会いに行くなら自分もフランスで短期のレッスンを受けてみたいと思い、ネットで探していたら、このアカデミーが一番上に出てきました。大学院ではドイツの作品を研究していたので、堅めでしっかりとした奏法には慣れていましたが、フランス流のレッスンはほぼ初めて。締め切りギリギリでしたけど「これは参加したい!」と。
―実際にピエール先生の授業を受けて、如何でしたか?
ピエール先生の脱力が効いた、自然に軽く弾く感じがすごく印象的でした。フランス音楽は色彩やグラデーションが繊細で、ドイツ音楽みたいに“始まりと終わりが明確”じゃない。実は、ずっと苦手意識を持っていたんです。大学院ではドイツ語やイタリア語を授業でとっていたのでなんとなくイメージできたのですが、フランス語はまったく分からないので、楽譜を読んでいてもイメージが掴みにくくて――学生時代に泣きながら練習したこともありました。
―そんな苦手意識がある中で、アカデミーに参加されたというのは、大きな転換ですね。
演奏する時にはどうしても「正確に弾かないと」とか「間違えちゃいけない」という考えが先行するせいか、身体が縮こまって息が止まり、そのために“真面目すぎる”とか“音楽が四角い”と言われていて、悩んでいました。ところが、ピエール先生のレッスンで呼吸法を教えていただいて、腹式呼吸のような感覚を意識することで、理想に近づけた瞬間があったんです。これまで具体的に呼吸に向き合ったことがなかったので、大きな発見でしたし、音が明らかに変わりました。他の受講生の聴講を通しても、呼吸が音に影響することが客観的に分かりました。今回のアカデミーをきっかけに、短期間でもいいのでフランスに行き、ピエール先生のレッスンをもっと受けてみたいと思うようになったのですから、大きな転換だと思います。
―レッスン以外にも、アカデミーならではの経験はありましたか?
リゲティ先生(チェロ)と室内楽を演奏するプログラムにも参加しましたが、先生のチェロの音が隣から聞こえるのがもう…幸せでした。室内楽が本当に好きです。卒業してから機会が減っていたので、あの時間はとても貴重でした。
―2回のリハと1回のゲネプロだけでコンサートに挑むという、密度の高い共演プロジェクトでしたね。他の受講生との交流もありましたか?
はい、ヴィオラは参加者が少なかったので皆と話す時間がたくさんありましたし、奏法について語り合うのはすごく楽しかったです。お世話になった通訳の方なども一緒に、先生とランチをしたことも良い思い出です。レッスンは緊張感に溢れていましたが、終わってみると楽しさが上回っていたと思います。
―今このアカデミーのHPをご覧になって、参加を考えている方々にメッセージをお願いします。
私にとっては、純粋に音楽を楽しむために、どうしたらよいかということを探す期間でもあった気がします。レッスンそのものも素晴らしいのですが、他の参加者のレッスンを聴く機会も多くて、刺激的で学びの多い時間でした。私自身、これまで1週間程度の講習会には参加したことがありましたが、2週間にわたってフランス人の先生とじっくり向き合える機会はとても貴重だと感じます。コンサートなどのイベントも多く、プログラム全体がバラエティに富んでいます。1週間では物足りないと感じる方にも、2週間という期間は春休みとも重なり、参加しやすいのではないでしょうか?いきなりフランスに行くのは少しハードルが高いという方にとっても、このアカデミーはその一歩として最適な環境です。会期中はフランス語が飛び交う環境でレッスンが行われますから!今はオンラインで多くの情報が手に入りますが、やはり実際の体験に勝るものはありません。私の周りにも、コロナ禍で留学を諦めた友人が数多くいました…。「思い立ったら吉日」と言いますが、私もホームページを見てすぐ応募しました。参加して損することは絶対にありません。このタイミングを大切にして、ぜひ挑戦してほしいです。


|
Vol.4 橘和美優さん(2025年 レジス・パスキエ教授 ヴァイオリンクラス受講生/パリ・エコール・ノルマル音楽院スカラシップ受賞者)
 幼少期からヴァイオリンとともに歩み、国内外の舞台で確かな実力を示してきた橘和美優さん。2023年には、世界的なロン=ティボー国際音楽コンクールで第5位に入賞し、若き日本人ソリストとして注目を集めました。表現力をさらに深めるため、今年も京都フランスアカデミーに参加。レジス・パスキエ氏の薫陶を受けた10日間を、「音楽表現の幅を広げた、成長の10日間」と振り返ります。2025年度パリ・エコール・ノルマル音楽院のスカラシップにも選ばれ、夢の舞台は次の章へと続いています。そんな橘和さんに、お話をうかがいました。
幼少期からヴァイオリンとともに歩み、国内外の舞台で確かな実力を示してきた橘和美優さん。2023年には、世界的なロン=ティボー国際音楽コンクールで第5位に入賞し、若き日本人ソリストとして注目を集めました。表現力をさらに深めるため、今年も京都フランスアカデミーに参加。レジス・パスキエ氏の薫陶を受けた10日間を、「音楽表現の幅を広げた、成長の10日間」と振り返ります。2025年度パリ・エコール・ノルマル音楽院のスカラシップにも選ばれ、夢の舞台は次の章へと続いています。そんな橘和さんに、お話をうかがいました。
―既に国内外でその実力を発揮しておられます。今回のアカデミーで、「新たに得たもの」について教えていただけますか?
パスキエ先生には、作品の背景や技術的なことをたくさん教えていただきました。秋に控えている演奏会のために、モーツァルトの作品を用意したのですが、オーケストラと共演するソリストとしてのコツ、音の出し方、指揮者への合図、立ち振る舞いに加えて、身体の使い方や、私が「弾きにくいな」と感じていた部分の原因とその解決策も見出していただきました。「練習を重ねれば弾ける」という単純な技術の問題ではなくて、もっと深い部分への考察があり、レッスン中は常に「目からうろこ」状態でした。自分はまだまだだと痛感しました。
―レッスンをすべて終えて、最も印象に残っていることを教えてください。
パスキエ先生の表現力です。作品のイメージを伝えるための身振り手振りや表情――体全体を使って表現する姿に、ヨーロッパならではの文化を感じました。日本人が自然に盆踊りを踊るのと同じ感覚なのかな(笑)? 日本でのレッスンではなかなか味わえないダイナミズムを感じ、イメージが作りやすかったです。
―確かに。レッスンを拝見させていただきましたが、パスキエ先生は椅子から立ち上がったり、腕を大きく動かしたりして、それこそ通訳の方や伴奏の方も一緒に巻き込んで、レッスンを作り上げているような雰囲気を感じました。
そうです!パスキエ先生のレッスンを受けることができたことは、私にとって大きな転換期でした。アカデミーでは、同じ先生に5回、1時間以上もレッスンしていただけます。しかも、毎回素晴らしい伴奏付きで、充実感と学びの深さは計り知れないです。ヨーロッパで活躍している先生方のレッスンを、このような形で日本国内で受ける機会は、なかなかないと思います。聴講制度を利用して他の受講生のレッスンを見ると、「あ、この曲を弾いてみたい」と思うことも多く、もちろん、自分のレッスンも聴講されることがありますが、逆に程よい緊張感を持ちながら演奏できるので、それも良い経験になりました。
―東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、東京藝術大学を首席で卒業し、東京音楽大学大学院へ進むなど、着実に演奏家への道を歩んでおられますが、橘和さんはソリストを目指しているとのこと。その理由を教えていただけますか?
室内楽もオーケストラも、何にでも挑戦していきたい気持ちはあります。ただ、コンクールで賞をいただくたびに、「もっと上手くなりたい」という意欲が湧いてくるんです。ソリストを目指しているのは、自分自身の技術力を磨きたいからかもしれません。
―パスキエ先生のレッスンを受けて「自分はまだまだだと感じた」と言っておられたように、目指している演奏家や、演奏における理想的な音色などがあるのでしょうか?
作曲家の個性を尊重しながら、基本には忠実に、それでいて演奏者自身の良さも伝えられる演奏が理想です。パスキエ先生もその点をしっかり見抜いていて、私の個性や表現したいことを尊重しながら、作曲家の意図から逸脱しないように導いてくださいます。個人的には、カナダのバイオリニスト、ジェイムズ・エーネスが大好きです。
―ちょうどこの取材が始まる直前に、2025年度のスカラシップを獲得されたという連絡を受けられました。おめでとうございます。感想を聞かせていただけますか?
まさか自分が受かるとは思っていなかったので、本当に驚きました。どうしてもパスキエ先生に師事して研鑽を積みたかったのですが、正直、あまり期待はしていなくて、落ちた場合のことを考えて、他の受験方法も調べていましたし、もしダメだったら、すぐに別の方法で留学準備を始めようと思っていたくらいです。だからこそ、とても嬉しいです。もちろん心配もありますが、それ以上にワクワクしています。現地の空気や言語を肌で感じたら、きっと自分の音楽も大きく変わるだろうという期待でいっぱいです。ただ、フランス語は……どうしよう(笑) 今から頑張って勉強します!
―ぜひ、留学中や留学後のお話も聞かせてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。


|
Vol.3 上村夏子さん(2025年 フローラン・エオー教授 クラリネットクラス受講生)
 母と姉の影響でクラリネットを始めた上村夏子さん。中学時代のソロコンクールをきっかけに、本格的な指導を受け始めてからはその魅力にどんどん引き込まれたといいます。現在は東京音楽大学クラリネット専攻の4年生として研鑽を積みつつ、フローラン・エオー氏との出会いからフランスでの学びに強く惹かれ、留学を視野に入れて準備中。京都フランスアカデミーでの経験は、「音の革命記念日」と語るほど大きな転機となったとか。そんな上村さんに、お話をうかがいました。
母と姉の影響でクラリネットを始めた上村夏子さん。中学時代のソロコンクールをきっかけに、本格的な指導を受け始めてからはその魅力にどんどん引き込まれたといいます。現在は東京音楽大学クラリネット専攻の4年生として研鑽を積みつつ、フローラン・エオー氏との出会いからフランスでの学びに強く惹かれ、留学を視野に入れて準備中。京都フランスアカデミーでの経験は、「音の革命記念日」と語るほど大きな転機となったとか。そんな上村さんに、お話をうかがいました。
―クラリネットを始めたきっかけを教えてください。
母と姉がクラリネットを吹いていたので、自然とその影響を受けていたと思います。もともと5歳からピアノを習っていましたが、小学4年生のときに吹奏楽部に入り、「何の楽器をやる?」と聞かれて、迷わずクラリネットを選びました。
―中学1年生のときに出場したソロコンクールが、ターニングポイントだったとか。
はい。通っていた中学校では、毎年1年生からひとり、地区の音楽コンクールに出場することになっていて、私は先生に選んでいただきました。初めてのソロで緊張しましたが、優秀賞をいただいて。それをきっかけに、プロの先生にレッスンをお願いすることになったんです。それまでは部活で、自己流の練習をしていたのですが、正しい知識と技術を学ぶと、音が変わり始めたのがすぐに分かりました。練習もどんどん楽しくなり、今でもその先生に師事しています。クラリネットの楽しさを教えてくれた恩師です。
―エオー先生との出会いも大きな転機だったとのことですが。
高校2年の夏、ビュッフェ・クランポン主催の欧日音楽講座に参加したときに、エオー先生のレッスンを初めて受けました。そのときのレッスンが本当に楽しくて!「もっとこの先生に習いたい」と強く思うようになりました。
―2023年にはパリでもエオー先生のレッスンを受けられたそうですね。
2週間パリに滞在して、エオー先生のプライベートレッスンを受けました。そこから「フランスで本格的に学びたい」という思いが強くなって、留学試験にも挑戦しました。ただ、結果は思うようにはいかず…。でも、どうしても諦めきれなかった。そんなときに、先生から京都フランスアカデミーのことを紹介していただきました。
―今回のアカデミーで、特に印象に残っていることは?
2回目のレッスンで、ずっと悩んでいたアンブシュアについて、先生から大事なヒントをいただいたんです。それをもとにいろいろ試していたら、「これかもしれない!」と感じる瞬間があって。自分でも音の変化が分かりました。先生にも伝わったようで、「僕もうれしいよ」って言ってくださったんです。聴講していた仲間にも「革命だね!」と言われて(笑)。あの瞬間は、本当に大きな転機でした。
―「革命」という言葉が印象的です。
はい、私の中では「音の革命記念日」です(笑)。表現したい音が出せなかったもどかしさから抜け出せたような気がして。あのレッスンで、自分の演奏が一段階、変わったと感じました。
―エオー先生のレッスン、どんなところに魅力を感じますか?
レッスンを受けるたびに、自分の視野が広がるんです。今の自分に足りないところを、明確に、そして優しく教えてくださる。やるべきことがクリアになるので、短時間のレッスンでも確実に成長できます。それに、最近では先生の日本語力が本当にすごくて…語彙が格段に増えているんです(笑)。そうやって、日本にも愛着を持ってくださっている。音楽だけじゃなく、人としてもすごく尊敬できる方です。
―アカデミーの魅力は、どんなところにあると思いますか?
プロや留学を目指して受講するのも素晴らしいと思いますが、アカデミーの魅力はそれだけではないと思います。クラリネットの魅力や音楽の楽しさを、改めて感じられる場、と言ったらいいでしょうか?聴講レッスン制度もすごくよい!仲間の成長から刺激をもらえるし、自分のやる気にもつながります。2週間という期間も、しっかり自分に向き合える長さです。
―これからの目標を聞かせてください。
今は、再び留学に挑戦する準備をしています。これまでクラリネット一筋の人生でしたが、気づけば、それ以外の世界に触れる機会が少なかったなと思っていて。「音楽は経験が物語る」という言葉が心に残っています。だからこそ、芸術の街・パリで、自分の素養を深めたい。演奏だけではなくて、喜びや悲しみや怒りや苦労をすることで、自分の中の“引き出し”を増やしたい。演奏家としても、人としても、一回り大きくなれたらと思っています。
Vol.2 神田真秀さん(2025年 アンヌ・ガスティネル教授 チェロクラス受講生/ディアナ・リゲティ教授 特別講座 室内楽 受講生)
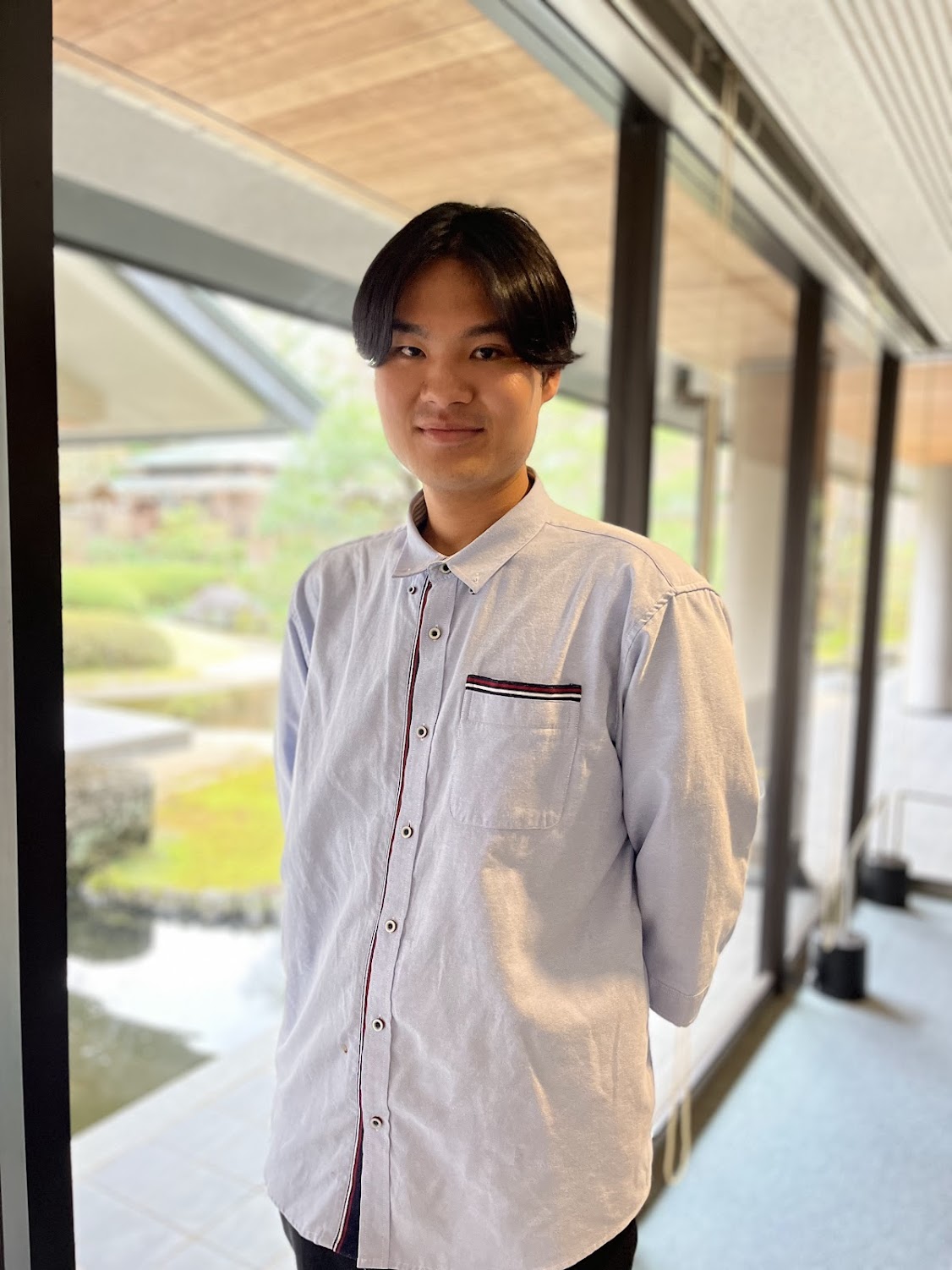 少年時代には野球とチェロを両立させていた神田さん。現在は京都市立芸術大学弦楽専攻2回生ながら、すでにCD収録や多くのコンサート出演の経験を積んでいます。尊敬するラファエル・ベル氏が指導するベルギーの音楽大学への留学を目指し、さらなる音楽の深まりを追求している神田さんに、お話をうかがいました。
少年時代には野球とチェロを両立させていた神田さん。現在は京都市立芸術大学弦楽専攻2回生ながら、すでにCD収録や多くのコンサート出演の経験を積んでいます。尊敬するラファエル・ベル氏が指導するベルギーの音楽大学への留学を目指し、さらなる音楽の深まりを追求している神田さんに、お話をうかがいました。
―室内楽のCD収録をはじめ、すでに数多くの演奏会に出演されておられますが、まずチェロを始めたきっかけを教えてください。
音楽好きな母の勧めで、5歳のときにチェロを始めました。とはいえ、中学2年生まではピッチャーで4番を任されるほどの「野球少年」でした。週末に野球の試合とチェロのレッスンが重なるたびに、「え~~!」と文句を言いながら、バットとグローブを急いでチェロに持ち替え、渋々ながらも、音楽には触れていたーそんな少年時代でした。
―今でいう「二刀流」ですね。神田さんは「京都フランスアカデミー」の創設にも関わったヴァイオリニスト・森悠子先生とご縁があったそうですが。
はい。小学3年生の頃から、森先生が主宰されていた子ども向けの室内楽講座「プロペラプロジェクト」に参加していました。ただ、当時はとにかく野球一筋で(笑)。チェロで演奏するのもジブリの曲やバッハのやさしい小品程度。それでもチェロを続けてこられたのは、「プロペラ」では世界各国で活躍するプロの演奏家たちの音に触れられたからだと思います。彼らの演奏は、音の力で胸を打つようなインパクトがありました。
中学1年生のときに、フランスで講習会が開かれると聞きました。どうしても参加したくて、両親を説得しました。「チェロのため」というより、「フランスに行ってみたかった」が本音です(笑)。でも、この2週間が、チェロとの関係を見つめ直すきっかけとなったのです。
講師のひとりであるチェリスト、ラファエル・ベル先生の演奏に衝撃を受けました。ベル先生はアントワープ交響楽団の首席チェロ奏者です。プロの音色と、孫に接するように優しく丁寧に指導してくださることがうれしかった。なにより、参加者たちの、真剣に音楽と向き合っている姿が、とにかくカッコ良く思えたんです。僕が「音楽を真剣にやろう」と思うきっかけは、このフランスでの体験です。自分にとって大きな意味を持っています。
―中学時代の「野球少年」から一転、京都市立京都堀川音楽高等学校、そして京都市立芸術大学へと進学されました。今年がアカデミー初参加とのことですが、何か“気づき”はありましたか?
僕は腕が長いので、どうしても余ってしまい、手首が不自然に折れてしまうクセに悩まされていました。今回指導してくださったアンヌ・ガスティネル先生は、右手の奏法に特化した指導法をお持ちで、体の使い方を毎回とても丁寧に教えてくださいました。次第に手首の動きが楽になり、音色に明らかな変化が出てきたのは、無意識に負担をかけていた動きがなくなったせいかもしれません。小さな変化ですが、積み重なって大きな音の変化につながることを実感しました。これは、非常に重要な気付きです。
―他の受講生のレッスンも聴講されましたか?
もちろんです!ほぼ全ての公開レッスンに足を運びました。どの楽器のレッスンでも、身体の使い方に関する指導は参考になりましたーたとえば、譜面を見るためにうつむく姿勢や、奏者が音を出すときの体の向きなど、演奏の背景にはたくさんの身体の工夫がある。きっと僕自身が室内楽を好み、他の楽器と音を合わせることに関心があるからこそ、こうした視点に敏感なのかもしれません。楽器が違っても、演奏における共通点は多く、また日本とフランスの解釈の違いを直感的に感じ取ることもあり、本当に学びの多い時間でした。
―神田さんは「受講生コンサート」に選ばれましたが、実際に演奏してみて、いかがでしたか?
まずは、他の出演者のレベルの高さに圧倒されました。どの出演者も本当に素晴らしくて、口が開いたまま(笑)。吸収したいヒントが無数にあって、自分の演奏にも取り入れたいことばかりでした。
―神田さんの演奏も印象的でした。満足できる内容でしたか?
演奏したのはドヴォルザークのピアノ五重奏曲。冒頭がチェロのソロから始まるので、かなり緊張しました。音の方向性について何度もメンバーと議論を重ねて、それでも答えが出ない箇所もありましたが、終わってみれば、「楽しかった」のひと言です。ほかのメンバーは全員東京からの参加だったので、「今度は東京で会おう!」と約束しています。こうした繋がりが得られたことも、かけがえのない財産ですね。
―アカデミーでの体験を振り返ると、いかがでしたか?
アカデミーでの2週間は、今までの音楽人生の中でも、「過去一」充実した時間だったと断言できます。先生方の熱量はもちろんですが、通訳や伴奏者の方々の手厚いサポートのおかげです。日本語が通じなくても、通訳の方々がこちらの意をくんで、細やかなサポートをしてくださったおかげで、自分のキャパシティを超えるほどの情報量を得ることができました。ここまで夢中になって音楽に没頭できる環境は、なかなかありません。この2週間は貴重な「宝物」になりました。「絶対に受講すべき」だと言いたいし、受講生コンサートも、もっと多くの方に聴いてほしい、多彩でレベルの高いコンサートでした。
―今後の音楽活動の目標を教えてください。
森先生からは、何度も「マシューくんにはぜひ留学してほしい」と言われてきました。尊敬するラファエル先生に師事したいという思いが強いので、先生が教鞭をとられているベルギーの音楽大学への留学を目指しています。さまざまな国の人と出会い、現地の文化を肌で感じながら、自分の音も、音楽への理解も、更に深めていきたいです。


|
Vol.1 菅沼千尋さん(2025年 マリー=テレーズ・ケレール教授 声楽クラス受講生)
 小学5年生から声楽を学び始め、東京音楽大学・大学院で研鑽を重ねてきた菅沼千尋さん。現在は、演奏と指導の両面で活動の幅を広げています。長年の蓄積を携えて臨んだ今回のアカデミーでは、表現の深さと声の可能性に真摯に向き合う姿が印象的に残りました。各クラスから選抜された受講生による修了コンサートでは、歌劇《ハムレット》より〈私を遊びの仲間にいれてください〉を通して、作品に内在する感情を丁寧にすくい取るような歌唱を披露してくれました。
小学5年生から声楽を学び始め、東京音楽大学・大学院で研鑽を重ねてきた菅沼千尋さん。現在は、演奏と指導の両面で活動の幅を広げています。長年の蓄積を携えて臨んだ今回のアカデミーでは、表現の深さと声の可能性に真摯に向き合う姿が印象的に残りました。各クラスから選抜された受講生による修了コンサートでは、歌劇《ハムレット》より〈私を遊びの仲間にいれてください〉を通して、作品に内在する感情を丁寧にすくい取るような歌唱を披露してくれました。
―声楽を始めたきっかけを教えてください。
小学5年生の時に学校に合唱団ができ、「絶対入りたい!」と父にお願いしたところ、「下手だと迷惑をかけるから基礎からちゃんと習いなさい」と言われたのがきっかけです。もともと音楽は好きで、ピアノは4歳から続けていました。音楽が身近にある家庭で育ち、声楽の世界にも自然に入っていきました。
―小学5年生からというのが驚きですね。どのような先生に習われたのですか?
町の音楽教室にいらした、オペラ出演もされるテノールの先生です。その先生の影響でオペラの曲にも親しむようになりました。
―高校進学時も音楽の道を考えていたのですか?
音楽高校に行く選択肢もありましたが、両親の勧めで普通科に進学しました。ただ、声楽のレッスンはやめずに中高とも同じ先生について、ピアノも同時進行で続けていました。学校外で声楽を学びながら、ピアノやソルフェージュは別の先生に習う、という高校時代でした。
―念願かなって音楽大学に進学し、大学院にまで進まれました。
東京音大に入って、ようやく「水を得た魚」のように学ぶ喜びに満たされたと言えます。まず、図書館で多くの楽譜に自由に触れられることがうれしかった!興味のある作品にすぐアクセスできる環境が整っているというのは、ありがたいことです。同級生と一緒に課題に向かって悪戦苦闘する日々を通して、仲間と学ぶ楽しさも実感しました。と同時に、思っていたほど自分が上手くない、ということも思い知らされました。
―それだけ技量や志しの高い仲間に囲まれていたということですね。大学院生活を経て、進路についてはどのように考えるようになったのでしょうか?
いくつか海外のアカデミーに参加し、大学の提携プログラムなども利用しましたが、なかなか「この先生だ」と思える方に出会えずに迷っていたら、大学でお世話になったフランス歌曲の先生にこのアカデミーを紹介され、参加を決めました。フランス音楽だけが目的ではなく、自分に合う先生に出会いたいという思いが強かったです。
―実際に受講してみていかがでしたか?
本当に来てよかったです!マリー=テレーズ先生は、生徒一人ひとりに的確なアドバイスをくださる素晴らしい先生です。自分の「本当の声」で歌うことを大切にされていて、無理な課題を与えず、10年・20年のスパンで成長を見てくださいます。これは他の生徒のレッスンを聴講していても、自分が受けていても感じたことです。大学院を卒業して1年ほどは、演奏会に出演したり、音楽学生を教えたり、フリーで活動することにはやりがいを感じますが、正直、“孤独”とも言えます。仲間がいて、同じ目標に向かって一緒に進んでいた大学時代と違い、今は「太平洋を一人で泳いでいる」ような感覚です。だからこそ、今回アカデミーで同じ志を持つ仲間たちに出会えたことは、とても励みになりました。
―クラスの雰囲気はどうでしたか?
声楽の受講生は私を入れて、11人。皆さん非常に熱心で、回を重ねるごとに変化していくのが分かりました。先生の指摘をすぐに反映しようと模索し、休み時間に話していても「そういうこと考えているんだ!」という発見の連続です。勉強熱心な方ばかりで、刺激的な2週間でした。
―日本とフランスの指導の違いはありましたか?
私は日本で非常にバランスの取れた先生に出会えているせいか、それほど大きな違いは感じませんでしたが、一般的には違いがあるのではないでしょうか。日本では若い時から大曲を歌わせる傾向があるような気がします。それが試験やコンクールでは高評価につながるのでしょう。でもマリー先生は、「声の成長」を大事にされておられました。
―「声の成長」とは?
喉というより、「声」そのものを育てる感じ、と言ったらいいでしょうか?声は、使って育てるもの。誤った指導を受けると声帯を傷めてしまう危険もあります。生徒一人ひとりの年や喉の成長具合に合わせた曲選びをしてくださる方だと思いました。
「声」ということで言うともう一つ。日本ではクラシックであまり使われない「胸声(地声)」を、フランスでは大切に扱うと教えていただきました。胸声を混ぜることで、オーケストラに負けない強い声をつくるという考え方が新鮮でした。マリー先生のレッスンは「圧倒的」。今、私自身も音楽学生を教える機会がありますが、伝えたいことをどう言葉にすればよいのか、もどかしさを感じることが多くあります。でも、マリー先生の指導方法を知り、自分の生徒にも使えるようなテクニックや練習方法に、「これだ!」と思う発見の連続。教える立場としても、たくさんのヒントをもらいました。
—今回のアカデミーでの経験を、今後にどうつなげようとお考えですか?
今後は、オペラの本場である海外に留学することを視野に入れています。ただ「海外だから」という理由ではなくて、信頼できる先生と連携しながら、確信を持って一歩を踏み出したいと思っています。この2週間は、自分自身と深く向き合いながら、素晴らしい先生方や仲間との出会いを通して、全国に同じ志を持つ人がいることを実感できる、貴重な期間でした。声楽を学ぶ者として、また教える立場の者としても、多くの学びがありました。この経験を糧に、ここからまた一歩ずつ前に進んでいきたいと思います。

●パリ・エコール・ノルマル音楽院スカラシップ過去受賞者リポート
2004年に開始されたパリ・エコール・ノルマル音楽院へのスカラシップ制度は、将来有望な受講生にフランス音楽留学への扉を開く機会となっています。過去のスカラシップ受賞者の声をご紹介します。
Vol.4 永井 啓子さん (2009年スカラシップ受賞、広島交響楽団ヴィオラ奏者)
 海外で音楽を勉強しようと思ったたことはなかったけれど、国内にいながら国外の教授のレッスンが受講出来る点に魅力を感じ、京都市立芸術大学大学院に在籍中の2009年、「アカデミー」に参加、見事スカラシップを受賞した。 4歳の頃からヴァイオリンを習っていたものの、演奏会に初めて足を運んだのは中学生の時。そしてその日耳にしたヴァイオリンの音色に衝撃を受けた。「自分もこんな音を出したい!」。それまで師事していた先生に相談し、指導者を代えて本格的に音楽に取り組み始め、この頃から音楽を専門に生きていこうと決意したそうだ。
海外で音楽を勉強しようと思ったたことはなかったけれど、国内にいながら国外の教授のレッスンが受講出来る点に魅力を感じ、京都市立芸術大学大学院に在籍中の2009年、「アカデミー」に参加、見事スカラシップを受賞した。 4歳の頃からヴァイオリンを習っていたものの、演奏会に初めて足を運んだのは中学生の時。そしてその日耳にしたヴァイオリンの音色に衝撃を受けた。「自分もこんな音を出したい!」。それまで師事していた先生に相談し、指導者を代えて本格的に音楽に取り組み始め、この頃から音楽を専門に生きていこうと決意したそうだ。
スカラシップを受賞して留学の機会は訪れたものの、「家族はまったく音楽に関心がなく、留学することを納得してもらうのが難しかった」そう。早くから楽器に親しんでいたが、「両親共に音楽とは全く無縁。進学に関しても『こうしなさい』『ああすれば』などと干渉された事は一度も無い」と言うのだから、驚きだ。兵庫県西宮市に生まれ、同志社女子大学学芸学部音楽学科でヴァイオリンを専攻。必修科目だったヴィオラの授業でその低音の魅力に惹かれ、同大学を卒業した2008年、京都市立芸術大学大学院にヴィオラ専攻で進学した。
大学院在学中のまさかの留学の話。「これはチャンスだ!と思いました」。休学を決意し、2009年9月にエコール・ノルマルへ。「行っちゃった、という感じ」と、朗らかに笑顔を見せる。
降って沸いたようなフランス生活。始めの4ヶ月間は音楽以外の理由で辛かったそうだが、フランスならではの思い出深いことも沢山体験した。オペラを聴きに行ったものの、美術係のストのために舞台装置が一切ない。しかし観客が舞台を盛り上げ、舞台と観客が一体になって演目は最後までやり通されたとか。また、17区のアパルトマンに住み始めてすぐこと。練習中に突然ドアが叩かれた。「もしかしたら音がうるさくて怒られるのだろうか!?」と、おずおずドアを開けると、40台とおぼしき住人が「セ・マニフィック! もっと弾いて!」と喜び勇んで飛び込んできた。自分の祖父がヴィオラを弾いていたので、永井さんのヴィオラの音色を耳にして嬉しくなり、思わず扉を叩いたのだと言う。
授業に関して印象的だったのはバッハの講義。それまでは「~しなければいけない」と、規則ばかりを指摘されてきたが、「バッハは自分だけの曲で良い」「自分の言葉で演奏しなさい」「この曲は食事をする前の曲だから、誰もちゃんと聴いてないよ!」など、今までの考えを根底からひっくり返されるような指導の数々。その一つ一つが忘れられないと言う。様々な個性を持った演奏を認める許容量の深さを実感。「もしずっと日本にいたら、この自由さが分からないままだったと思います。音楽を自由に作ることの楽しさ。でもその分、自分で考える事も必要。日本でダメだと言われてきた部分を厳しく追及していくことも必要だけれど、自分の演奏の良い部分を認めてもらい、かつ厳しい指摘もしてくれるレッスンが楽しかった」。
あっという間の1年間。「もっと準備をしていたら更により良いものになったかもしれません。特にフランス語を理解出来たら絶対違っていたはず」と、振り返る。レッスンは基本的に英語で進められたそうだが、「ノッて」くるとフランス語に。「細かい部分が分からず歯がゆかった」と肩をすくめるが、努力と勤勉さ、大らかな人柄で乗り越えてきたことが見て取れる。「面白い人や印象深い人、素敵な演奏をする人にたくさん出逢いました。一人ひとりの名前は思い出せなくとも、一緒に過ごした思い出深い時間は忘れられません」。
大学院に復学するため、2010年に帰国。翌年3月に同大学院を卒業。音楽に関してはほとんど一切干渉しなかったというご両親だが、一貫して言われてきたことは「独立すること」。インターネットで偶然見つけた広島交響楽団のヴィオラ奏者募集の記事。両親が共に広島県出身だったこともあり、オーディションを受けたところ、見事合格。2011年11月に正式に入団した。
それまでは好んで人前で演奏してきた方ではなかった。しかし今は仕事として、プロとしての演奏が求められ、その厳しさを痛感していると言う。全く知らない曲がどんどん舞い込んでくる。譜読みが追いつかない。「こんなに本番に緊張するはいやだ」と思ったことは一度や二度ではないとのこと。アンサンブルを演奏したいという意気込みを持った団員も多く、定期演奏会以外でも弾く機会が多いとか。その流れの速さに付いていけなくて自信を失いかけていたとき、先輩からアドヴァイスを受けた。「『緊張ばかりで楽しめない』『失敗しちゃダメ』でなくて、楽しむことを大事にしよう!」。意識を変えよう、そうでないとお客さんに伝わらないと、考えを改め始めたそうだ。
「良い演奏をしつつ自分も楽しむのは難しいことですが、素晴らしいソリストの演奏を耳にする度に、美しい音楽を身近に感じられるこの職場がありがたいと痛感します」と、笑顔を見せる。本番3日前のリハーサル。忙しい時期は月に2日間しか休みがないということもある。地方公演もあり多忙を極めるが、演奏会が終わると感想を言いにきてくれるお客さんもいるそうだ。月一回の定期演奏会には必ず団員全員分のシュークリームとおにぎりを差し入れるという、同楽団の「ファン」がいるとか。「若い子がんばれ!」「このオケの長年のファン!」と、いつも声を掛けてくれるその「ファン」の存在は、きっと計り知れない程大きいだろう。
忙しい仕事や練習の合間を縫って、2013年に再びアカデミーに参加。「仕事詰めの生活から少し抜け出して、外国の先生のレッスンを受けると、自分の考えが更に拡がります。それは音楽だけではなくて『生き方』そのものも含めてです。今後も休みが合えばアカデミーを受講したいし、機会があればもう一度フランスで学んでみたいです。その時はきっと、学生の頃とは違う留学になるでしょうね」。今は「言われてやることが全て」と肩をすくめるが、いつか自分で企画してヴィオラのソロや、ピアノとのデュオのコンサートを開きたいと、夢を語る。「アカデミー」の受講を考えている人には、「素晴らしい教授陣からはもちろん、共に受講する仲間に会うことで、自分の世界が拡がります。ぜひ挑戦してみて下さい!」。と、自身の体験を踏まえた言葉を聴かせてくれた。
ご両親からの「独立すること」という厳しく優しい言葉に応え、現在はプロとして活躍している永井さん。広島県のみならず、関西でも関西フィルにエキストラとして演奏することがあるそうだ。永井さんのヴィオラの音色を聴いて、子供の頃の永井さんのように、音楽の道を目指す子供達がきっとどこかにいるだろう。
Vol.3 松尾紗里さん(2009年スカラシップ受賞、ピアノ)
 留学する時期は人によって様々だ。松尾さんが京都フランス音楽アカデミー(以後アカデミー)を受講したのは、京都市立芸術大学ピアノ科に在籍していた3年生の春だった。最終学年を目前に控え、毎年アカデミーを受講していた友人や、新聞でアカデミーを知った母親から勧められたのがきっかけだったそう。クリスチャン・イヴァルディクラスを受講。「先生の音色に目が丸くなりました。自分の音と全く違ったのです。ものすごく素晴らしかった」。見事スカラシップを受賞したが、「留学するのは今じゃないと思い、辞退しました」。
留学する時期は人によって様々だ。松尾さんが京都フランス音楽アカデミー(以後アカデミー)を受講したのは、京都市立芸術大学ピアノ科に在籍していた3年生の春だった。最終学年を目前に控え、毎年アカデミーを受講していた友人や、新聞でアカデミーを知った母親から勧められたのがきっかけだったそう。クリスチャン・イヴァルディクラスを受講。「先生の音色に目が丸くなりました。自分の音と全く違ったのです。ものすごく素晴らしかった」。見事スカラシップを受賞したが、「留学するのは今じゃないと思い、辞退しました」。
ピアノを弾いていた4歳上の姉の影響で、生まれた時から音楽に親しみ、3歳で音楽教室に通い始めたが、ピアノを弾くことより作曲法や聴音、ソルフェージュなどの「表現すること」の方が楽しかったと言う。中学では陸上部に所属したり水泳を習ったりとスポーツにも励みつつ、高校は兵庫県の公立校で唯一「音楽科」のある県立西宮高校に進学してピアノを学び、「この先生に師事したい」という強い思いを抱いて、希望通りの大学に入学した。
ピアノの道を順調に進んできたように思えるが、「音楽教室で学んできた音楽的に表現する事や作曲が得意で、メカニカルな奏法の基礎を飛ばしてきたせいか、高校に入ってから小学生レベルの本当に初歩から手厳しくやり直されました」と、苦笑う。様々な学生が集う音大で、10代の頃から海外で研鑽を積んだ学生などにも出会ったが、自分は日本でもっと細かいニュアンスを習得する必要がある、時間と努力があればメカニカルなものはきっと会得出来ると信じて練習に励んできた。留学のチャンスは嬉しかったが、松尾さんが選んだのは大学院に進学すること。「小さい頃から学んできた表現することと音高・音大で学んだ奏法が、大学院に入る頃やっと合致しました」。そして2012年に同大学院を卒業し、満を持してその年の8月にパリ・エコールノルマルに留学した。
渡仏1年目の感想を聞くと、「自分の演奏が下手で雑になったような気がしました」という答え。「日本では『ここはダメ、ああして』と、きっちり弾くことを求められ、まるで細い平均台を渡るような気持ちだったのが、フランスではどの先生からも『あれをしてはいけない、これをしてはいけない』などと言われません。その代わり、『あなたの言葉で弾かないと意味がないじゃない』と、自分を表現することを求められます。フランス語でうまく答えられない分、ピアノで表現するしかなくて、曲を徹底的に調べ、より大げさに演奏するようになりました」。古典もバロックも今まで自分が思っていた以上に自由に演奏することが許された。「でも、表現しようとするだけだと見破られます。そこに意思がはっきりしないと納得してもらえない」。先生と意見の違いがあっても、ちゃんと意思を述べられるか、その人なりの考えがあるかどうかが鍵だという。「ペダルやテンポを揺らしてはいけないなどと言われてきっちり弾くより、人間性にあふれた演奏の方が受け入れられるのかもしれません」。
フランスでは学生でも人前で演奏する機会に溢れていると感じるそうだ。教会で演奏したことが2度あり、とても得難い体験だったそう。渡仏後すぐに挑戦したコンクールでは「聴衆賞」を受賞した。1位はフランス人、2位はロシア人と松尾さん。「1位の方は、演奏レベルより『私を見て!!』と訴えるオーラの方が印象的で、とても面白かったです! 逸脱していても魅力があればいいのかもしれません」と、声を弾ませる。
松尾さんは、日本で細かい技術や基礎を十分習得した後、より大きな「音楽的感覚」を身につける為に自分で時期をしっかり見極めてから留学した。エコール・ノルマルのクラスでは偶然にもアカデミー受講時に同じクラスメイトだった友人が2人もいて、とても心強かったと言う。「アカデミーのレッスンを受けた事がきっかけで素晴らしい先生や仲間に出会い、留学するという考えにも至りました。受講生仲間にも恵まれたけれど、通訳の方も素晴らしかった。奇跡に近い教授陣が集まり、他の楽器のレッスンも聴け、まるでプチ留学です」。日本にいつ帰るのかは「今まさに考えているところ」。エコール・ノルマルの卒業試験が無事に終わればパリのコンクールにも挑戦してみたいと、前へ前へと気持ちは進む。
夢は「いつか自分が作った曲をコンサートで演奏すること」。幼少の頃から培われていた「音のパレット」の豊かさが垣間見える。作曲も編曲も伴奏も楽しいと言う。2014年6月、フランス南部のカルカッソンヌとモンペリエで前述のコンクールの「報償コンサート」でソロ演奏することが決定。フランスの空の下、松尾さんのピアノの音が響き渡る。
Vol.2 大橋ジュンさん(2004年スカラシップ受賞、声楽家・ソプラノ)
 大阪音楽大学声楽科、同大学専攻科を修了後、母校の助手や大阪のプール学園高等学校の非常勤講師として務めるかたわら、関西各地で様々な賞を受賞していた大橋さん。仕事や自身の音楽活動で忙しいにも関わらず、2004年に開催された第15回京都フランス音楽アカデミー(以下アカデミー)に参加したのは「フランス歌曲に興味があり、仕事も春休みで丁度良い機会と思ったから」だと言う。
大阪音楽大学声楽科、同大学専攻科を修了後、母校の助手や大阪のプール学園高等学校の非常勤講師として務めるかたわら、関西各地で様々な賞を受賞していた大橋さん。仕事や自身の音楽活動で忙しいにも関わらず、2004年に開催された第15回京都フランス音楽アカデミー(以下アカデミー)に参加したのは「フランス歌曲に興味があり、仕事も春休みで丁度良い機会と思ったから」だと言う。
大学を卒業した直後から音楽講師の仕事に就いている。「人に教える事は好きです。教えると同時に自分に足りないものも分かります」。アカデミーでスカラシップを受賞した時には京都女子大でも講師として働いていたので、その年に渡仏する事は出来なかった。留学を決めたのは「人生の何かのきっかけになるかもしれないと思ったから」。翌年2005年に渡仏。「1年で何が出来る?」と、自問自答しながらの滞在だったという。パリでは画家を始め、何人もの学生に部屋を間貸ししていた初老の「ムッシュー」の家に間借り。ボジョレーの解禁日には手料理を振る舞い、週に一度はフランス語を教えてくれたと、懐かしむように話す。
パリに音楽留学する学生にとって、住んでいる部屋で音を出せるかどうかは大きな問題だ。大橋さんの場合は基本的に部屋で音を出すことが出来なかったので、練習は留学先のフランス高等音楽教育機関「パリ・エコール・ノルマル音楽院」でのみ。韓国人やスペイン人らと共に研鑽を積んだ。ドビュッシーやプーランク。フランスの空気に直に触れるにつれ、「この作曲家達がここで生きてきたのだと感動を覚え、歌詞に出てくる木々や花が想像しやすくなりました」。ドイツの森、フランスの森。「森」一つとってもそれぞれ違いがあり、そのニュアンスが歌に反映出来るようになったと言う。もちろん空気を感じるだけではなく、「パリに行くなら語学は必須」と、言い切る。「良いことを言われても意味が分からなければもったいない!」。学生には不可欠なVISAの手続きにしても、言葉の壁があるために苦労している人がいる。「時間がもったいない」。語学学校に通い、多国籍の友人らと交流を深めながら、「ムッシュー」のレッスンを受け続けた。「小さな子供が使うような音楽テキストを買って音楽用語を勉強したこともあります」と、当時を思い出して笑う。
一年という限られた時間を有効に使おうと、地道な努力を続けながら数多くのコンサートに足を運んだ。日本ではあまり観られないオペラやコンサートを聴き、「パリ・エコール・ノルマル」でレッスンを受けながら、日本での仕事の再開のめどもつけた。教壇に立つ仕事が決まった段階で帰国。「1年足らずの留学で何ができるかと言われると困るけど、『留学してみたかった』という知人は多い。今は留学するのに足踏みする傾向もあるようだけれど、何かのきっかけになる」と、期間に左右されない本場での勉強の意義を強調する。若い年代から留学する人も多いが、「30代で行ったからこそ落ち着いて勉強が出来た。語学学校でのレベル分けチェックや、多国籍の仲間が出来たことはとても良い経験。それに、パリに住んで初めて自分がメンタルな部分で島国の人間だなと思いました」。
帰国した後も大学や高校で教鞭をとりながら音楽活動を続けている。留学時に知り合ったクラリネット奏者の篠原猛浩さんと結婚。2013年12月には篠原さんらと共に、大阪市でプーランクの没後50年に寄せた記念コンサート「Fetes galantes艶やかなる宴」を開く。
アカデミーのスカラシップを受賞して留学してから8年、「音楽活動を続けようと思ったら、自分を高める為に仕事も必要」と言い切る。後進の指導に努めながらアンスティチュ・フランセ関西-大阪で、フランス語の詩の解釈を学ぶ講座に通い続けている。「これまではメロディーを優先に曲を選択していましたが、今では『この歌詞を歌いたい』と、歌詞の比重が高まっています」。常に勉強を怠らないその姿勢はきっと学生達にも伝わっているだろう。
Vol.1 白根亜紀さん(2005年スカラシップ受賞、声楽家・メゾソプラノ)
 2005年に開かれた第16回京都フランス音楽アカデミー(以下アカデミー)声楽の部に参加したのは、まだ京都市立芸術大学に在籍中の学生の時だった。既に、滋賀県の「県立芸術劇場琵琶湖ホール」専属の声楽家として活動していたが、あるリサイタルで知り合った伴奏者に受講を薦められたのがきっかけだったという。既に応募締め切りは過ぎていた。急いで書類を整え、音源を送ったところ、合格の通知が来た。
2005年に開かれた第16回京都フランス音楽アカデミー(以下アカデミー)声楽の部に参加したのは、まだ京都市立芸術大学に在籍中の学生の時だった。既に、滋賀県の「県立芸術劇場琵琶湖ホール」専属の声楽家として活動していたが、あるリサイタルで知り合った伴奏者に受講を薦められたのがきっかけだったという。既に応募締め切りは過ぎていた。急いで書類を整え、音源を送ったところ、合格の通知が来た。
「本場の講師陣が来日し、違う楽器のレッスンも気軽に見学出来る。びわ湖ホールでの仕事もあったのでレッスン全てには参加できなかったのですが、それでもたくさんの刺激を受けました」
スカラシップを受賞すれば一年間フランスに留学する機会を与えられるが、実はそのような賞があることを知らずに受講した。レッスンも最終日が近付いた頃、“フランスに行く気、ある?”と声楽担当教授のフランソワ・ル・ルーから通訳を通じて聞かれた時は、何のことか分からなかったと言う。 「行きたい気持ちはありましたが、仕事があったので即答出来ませんでした」。
やり甲斐のある日本での仕事か、フランスへの留学か。職場の担当者に相談したところ「折角なのだから行くべきだ」と背中を押してくれた。ひと月経たぬ内に留学を決意。携わっていた関西でのオペラ公演の稽古と、故郷の宮崎での留学準備を同時進行。公演が終わるや否や、「本当にフランスに行けるのだろうか」と半信半疑のまま機上の人になった。
アカデミーでの受賞から約半年後の2005年9月、フランス国内唯一の私立高等音楽教育機関、「パリ・エコール・ノルマル音楽院」に留学。一年間は瞬く間に過ぎた。「自分よりもっと上手な人の歌を聴いてしまった」「このままではダメだ」「一年で終わるのはもったいない」。溢れるような思いに駆られ、留学期間を延長するために「明治安田クオリティオブライフ文化財団」の「海外音楽研修生費用助成」のオーディションに応募。当時のびわ湖ホールの芸術監督・若杉弘の推薦状を手に、たった15分のオーディションの為に日本に戻った。面接が済み、パリに戻ってから届いたのは嬉しい合格の知らせ。それからはエコール・ノルマルの上級課程である第5課程、第6課程を見事修了。更に高等課程の“コンサーティスト”まで進み、結果を出した。
留学生活が全て順風満帆だったわけではない。声をつぶしてリハビリの為にロンドンまで通ったこともある。精神的にダメージを受け、歌えなくなった時もある。大切な試験を受けられない程のコンディションだった時もあった。そんな時にふとした縁で紹介されたのが、声楽家のクリスティーヌ・シュヴァイツァー。「目から鱗のレッスンでした」。リハビリを兼ねながらレッスンを受ける内に、自分の中の何かが開けていったと言う。
「『ここが変だからこうしようか』ではなくて、『今!この声いいよ!』と良い部分だけを取り上げてくれる。ネガティブな事は一切言わない」
喉と心のリハビリが効を証し、やっと声が戻り始める。パリに居を定めながら2008年に再び、びわ湖ホールの公演に出演。同年にはパリのシャトレー劇場でアジア人のコーラスを探していると聞き、オーディションを受けて合格し、パリの劇場の舞台に立った。シュヴァイツァー氏には今でも師事しているという。
「フランスに行く気、ある?」と聞かれ、咄嗟に“Oui”というフランス語が出てこなかったあの日から約8年。今現在はびわ湖ホール声楽アンサンブルのソロメンバーにも登録。2013年10月には同ホールのオペラに出演した。
「クリスティーヌ先生のように、ネガティブな事は言わず、良いもの=原石を見つけることに集中したい。子育ても一緒。その子だけの良いところを見つめていきたい」と、語る。アカデミーの受講を考えている音楽家達には、「自分にも言えることだけれど、何でもやってみないと分からない。可能な限り飛び込んでみる。そして自分を大切にして前向きに、ポジティブに!」とメッセージをくれた。アカデミーを通じた様々な出会いが、今も続いていると言う。「いつかアカデミーの卒業生でコンサートを開きたい」と、笑顔を見せてくれた。
「そしてこれからも可能な限り日仏間を行き来し、自分の歌を歌い続けたい」。
【ライタープロフィール】
治部美和
フリーランスライター。静岡生まれ京都育ち。パリ第4大学ソルボンヌ在籍中、日系企業の現地取材や撮影のアシスタント、通訳、広報誌の取材・執筆などを担当。日本で新聞社系の週刊情報紙の記者を勤めた後、プラハ、N.Y.やシカゴ生活を経て、現在東京在住。
