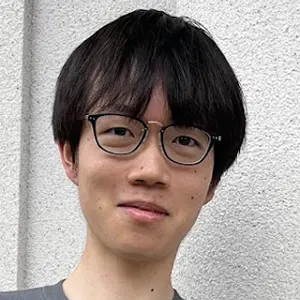
高校からクラリネットを本格的に学び、演奏と音楽研究の両面での探究を志している下村玄登さん。自由な表現を促すフランス流の指導や、多彩な仲間との交流を通して、「演奏の引き出しが一気に増えた2週間」と振り返ります。大学院進学を機に、「演奏すること」「考えること」の両面から、音楽への理解を深め続けたい――そんな下村さんに、お話をうかがいました。
「刺激を糧に、音楽の深みをさらに追求」
―クラリネットを始めたのは高校から、ということですが、音楽はいつから始められましたか?
6歳のときにピアノを習い、小学4年生でフルートにも少し触れました。その後、中学校の吹奏楽部でバスクラリネットを始めました。
―小さな頃から様々な楽器に触れてこられた中で、特に中学時代にバスクラリネットを選ばれた理由はなんだったのでしょうか?
主旋律ではなくて、低音を支える役割に魅力を感じたのだと思います。音楽全体を下から支えるようなポジションに惹かれて、中学3年間はバスクラ一筋でした。
―絶えず音楽を続けながら、あえて音楽高校ではなく普通科の高校を選ばれたと伺いましたが?
そうなんです。私立の普通科に進学しました。ただやはり音楽は続けたかったので、吹奏楽部に入部したのですが、小規模で経験者が少なかったからか、「バスクラができるならクラリネットもできるよね!」と言われ(笑)、そこからクラリネットに転向しました。「いつクラリネットを始めたの?」と聞かれたら「高校から」と答えていますし、実際、本格的に始めたのは高校からです。
―高校からクラリネットを始められて、そこから音大に合格されるまでの努力に、並々ならぬ努力と集中力を感じます。きっと、それまで積み重ねてきた音楽経験が大きな支えになったのではないでしょうか。この春からは大学院に進まれます。直前のこの時期に、アカデミーに参加を決めたきっかけを教えていただけますか?
大学の同門の先輩や同期に受講経験者が多かったことがきっかけです。門下全体で参加するような雰囲気があって、自然と「自分も受けてみよう」と思いました。大阪にいながら、京都で海外の先生のレッスンを受けられるという距離感も大きなポイントでした。実はエオー先生は僕の通っている音大の教授の一人です。ただ、4年間のうち、レッスンを受けたのは3回生のときの1度だけ。授業で忙しかったので、外部のレッスンを受ける機会もなかなかなく、クラリネット単体の講習に参加するのは、今回が初めてでした。
―実際にご自身が参加されて、いかがでしたか?
とても濃密な2週間でした。まず、生徒の幅が広い。関東の音大生とここまで密に交流するのは初めてで、非常に新鮮でした。同じ音大生でも、普段接点のない学校の学生の音を聴けたのは大きな収穫です。
―レッスンの内容で、何か印象深かったことはありますか?
音楽の「揺らがせ方」や「節回し」の捉え方が違うことです。言語が違うから、考え方も当然違ってくるのかもしれませんが、日本式の教育にはないような指導もあり、それがすごく刺激になりました。「こんなに大胆にやっていいの!?」と思うような提案もありましたが、それが自分の“引き出し”を増やしてくれます。演奏者にとって表現の幅が広がるのはとても大事なことです。
―例えばどんな点で下村さんの“引き出し”が広がったのでしょうか?
技術的な指導はもちろんですが、表現の自由度が高い曲-特に19世紀以前のロマン派あたりの作品は、演奏者に委ねられる部分が多いです。そうした曲での“解釈の幅”を教えてもらえたことが大きかった。
また、今回プーランクのクラリネットソナタも持ち込みましたが、楽譜に細かい指示が多くて、それをどう解釈して表現するかが自分の課題でした。プーランクのようなフランス人の作品は、先生の“主戦場”です(笑)。作品の背景に関してはもちろん、たとえばこのソナタは遺作で、初演されたときにはプーランク本人はもう亡くなっていたけれど、その初演の伴奏者とエオー先生が知り合い――たしか「師弟関係だった」とおっしゃっていたかな?―つながりがあったそうなんです。すごいことですよね! プーランク本人に近づいたような気持ちになれて、音符の意味合いが変わってくるんです。これまでだったら、楽譜を読んで理屈で「こういうものかな」って考えるだけだったのが、そこからさらにもう一歩踏み込んで、理論を超えられる。そういう指導を受けられるのは、本当に大きいことでした。
―エオー先生のレッスンがどれほど良い刺激を与えてくれたのかが伝わってきました。そのうえで、これから下村さんは大学院でどのように音楽と関わっていこうとお考えですか?
実は、音楽の研究に興味があります。
―音楽学ということですか?
はい。大学院では演奏だけでなく、音楽の研究にも取り組みたいと考えています。もちろんクラリネットに関係する内容になりますが、たとえばクラリネット作品への音楽史的アプローチとか。実は音大に入る時点で、音楽学の道に進むか、演奏に進むかで迷ったくらいなんです。とはいえ、演奏の裏付けは必要だと思っているので、そういう意味でも、現地の空気感が感じられたり、受講生それぞれの作品へのアプローチが直に見聞きできたりするこのアカデミーのような場は“引き出し”を増やすためにも、とても重要です。
―レッスンを終えて改めて感じることはなんでしょうか?
先生からだけでなく、生徒間の刺激がすごく大きかったことでしょうか。今回来て驚いたのは、関東からの受講生がとても多かったこと。フランス留学から帰国して受講しているという方もいらっしゃいました。学生だけでなくて、音楽を仕事にされているプロの方もおられて、生徒の幅がとても広かった。彼らから受ける刺激は大きかった。生徒同士の影響は、先生から受けるものと同じくらい大きいんじゃないかなと思います。
―では最後に。このアカデミーでの時間を、下村さんの一つの物語にするとしたら、どんなタイトルになるでしょうか?
めちゃくちゃ難しい(笑)。――――「刺激」、でしょうか。
―大学院という新しいステージで、アカデミーで感じた「刺激」が、演奏の喜びはもちろん、音楽を学び、考える楽しさにも広がっていくことを願っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
